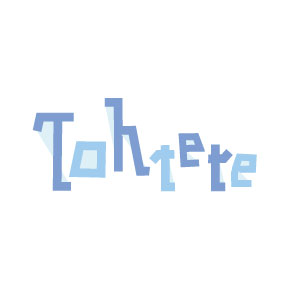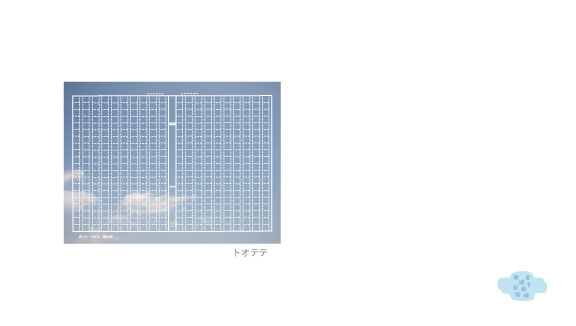序:暮らしと染色
3.染色と着色

・色料と色素
物に色をつけて、これを美しく彩(いろど)る材料のことを、色料と言います。
これとは別に、色素という言葉があります。それは、木や草の花や葉の含んでいる、あらゆる色の材料を全部含んでいて、その中には、実際に物を彩る材料として利用できないものがたくさんあります。
そこで、そういうものと区別して、染色や着色に利用する色の材料のことだけを、特に色料と言います。

・染色と着色
色料を用いて物を彩る場合、それには、二つあります。一つは染料による染色、もう一つが顔料による着色です。
染色とは、色料が繊維の内部にまで入って行って、そこで繊維と結びついている(これを染着という)ものを言います。また、着色とは、色料が繊維の中には入らずに、顔料が外面に附着しているものを言います。

・染料と顔料
染色に使われる色料は、染料と言います。また、染色されないで、単に附着による着色の材料としてのみ使い得る色料は、顔料と言います。
染料という名称は、染色の材料、あるいは染色用の色料ということです。顔料という名称は、顔色の材料、あるいは顔色用の色料という意味です。

・着色と顔料
顔色とは、もともと顔の色のことであり、顔料とは、始めは紅(べに)のことでしたが、それがおしろいや眉墨をも含むようになり、やがて意味が広くなって、着色の材料はすべて顔料と言うようになりました。
顔料は、繊維の外側に附着しているだけなので、そのまま着色したのでは色が落ちます。そこで膠(にかわ)とか、卵白、大豆汁(ごじる)、蝋、油、漆、ゴム、樹脂、その他いろいろの膠着剤を使って、それを繊維に膠着させることが必要です。

・染色と染料
染色の作用として、染料は、必ず一度水にとかした形にする必要があります。いろんな方法で、一度、染料を水にとかします。そうでないと、粒子が大きくて、繊維の中に侵入して行かないからです。
染料による染色は、色料が繊維の内部で染着しているので、洗っても、こすっても、そう簡単に色が落ちてくる心配はありませんが、染料の染色がうまくいっていないと、顔料と同じように、繊維の表面に染料が附着している状態になるので、色が落ちてくる可能性があります。
このように、仮に染色をしても、やり方が適切でなければ、染料が繊維の内部に入らずに、外面に附着している状態となり、色は、”こする”と”おりる”、ということになります。

参照:「日本の草木染」上村六郎(著)