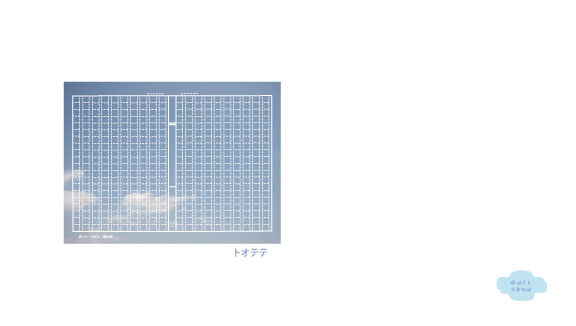「ホークー・レッア 1979」(1:誰も来ない部屋)
川面の水草が映え、セルリアンの空にひつじ雲が広がる、マノアの初夏の日に見守られて、コーサフは、ファイルに綴られた一つの資料を見直していた。
窓明かりに安らぎを感じながら、資料の三つの写真、四つの写真を眺めては、そこに書かれた文章を読み進めた。
庭では白いプルメリアの花が、通り過ぎる風や、揺れ動く木の葉と一緒になって、柔らかい陽の光を楽しんでいる。
彼女は、誰も来ない部屋でひとりで過ごす、この貴重なひとときに、とても神聖な響きを感じていた。

僅かなこの時間が、与えられたひとつの恵みだと知ると、より深遠さが増してくる。そしてそれは早朝の散歩のように風を追っていくこともない。
1979年の夏、コーサフは、1868年から1924年までのハワイの日系移民の人たちが着ていた衣服を、東アジアの衣装資料として、その聞き取りの調査を始めようとしていた。
外からの穏やかな日差しが、何かしら、無条件に与えられた約束でもあるかのように、窓からのひとつの影を少しずつ長くしていく。
この調査は、ハワイの日系移民一世の人たちの、被服に対する風習とその変遷を知ることにあり、それは、今まで学術的に誰にも取り上げられることはなく、抜け落ちていた。

資料から顔をあげると彼女は、ふと息をついて目の前のコップに半分ほどの水を注いだ。水差しは、太い縦縞模様が刻まれたガラス製で、中に入っている常温水に、どこかしら天然の涼し気な感じを与えている。
縁のまわりに、五つ葉のモチーフを六つ配した、陶器のコップを手に取り、コーサフは、その水を少し口に含んだ。常温に保たれた水は、彼女の体の中で次第に浸透していった。