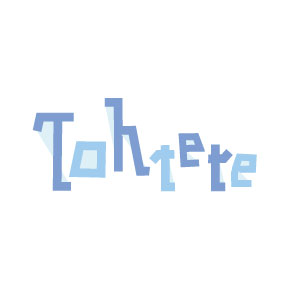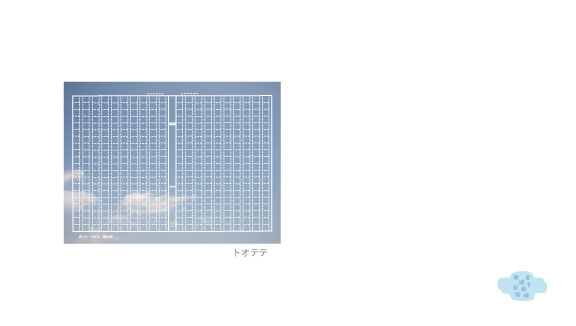序:暮らしと染色
2.色合い

・美しい色
それは、それを見た場合に、私たちの気持ちを浄化してくれる色のことです。
具体的には、その色を見ていると、気持ちがなごやかな、のどかな、ユッタリした平和な感じになる色のことで、落ち着かない、不安な、イライラする感じになる色は、美しくない色です。
第二の例として、その色が清らかな、スガスガしい、スッキリした気持ちを与えてくれる色も美しい色で、どことなく濁った、きたならしい、ゴタゴタした感じを与える色は、美しくない色です。
最後に、明るい、いきいきした気持ちを与えてくれる色は、美しい色で、見る人に、暗い、憂うつな感じを与えるような色は、美しくない色です。
美しい色を生活に取り入れるということは、それによって、生活そのものを美しくすることになり、ここに倫理的、社会的な意味や価値を持つことになります。そして、それらの色の使い方を見ると、その国の文化性が分かるように思われます。

・色から受ける感じ
色の美しさ、色から受ける感じは、人によって多少の違いがあり、民族の習慣や歴史や時代によっていくらかの違いのあるのは確かですが、それは、一小部分であって、大体において、世界共通だと言えます。
例えば、アイヌの人たちが、黄を神様の色として尚(たっと)んだり、沖縄では、白をお葬式の色として縁起が悪いと言うのを聞きますが、黄色い色から受ける直接の感じ、明るい、輝かしい感じ、又、白い色から受ける直接の感じ、清浄潔白な、清らかな感じというものは、大体どこにおいても変りがありません。
緑のもつ静的な、平和な感じ、赤のもつ動的な、元気な感じ、水色のもつ冷たい感じ、橙色の暖かい感じというものも、どこの国の人にも共通で、万人共通の感じと言えます。
ただし、その人が持つ社会性や文化意識の違いは、かなり大きいものがあります。そして、一つの色の美しさの問題と同じく、色の調和の問題においても、この点は全く同じです。

参照:「日本の草木染」上村六郎(著)