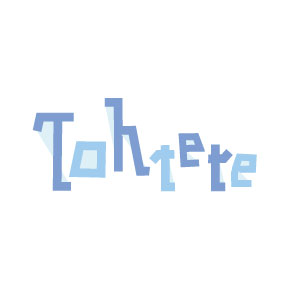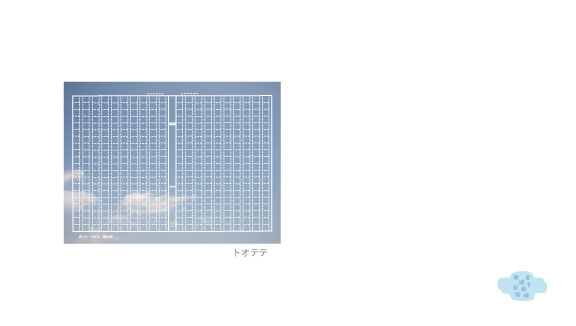序:暮らしと染色
4.あがもふひとの

・うつろひやすく
天然のものの持っているさまざまな色、例えば、花や果実の色というものは、必ずしも染料として利用できるものではありません。それらの色素には、染着性がないものが多く、繊維に染着しません。仮に繊維の内部にまで入って行ったとしても、洗濯ですぐに洗い落とされてしまいます。従ってこれを実用的な染色に利用することはできません。

・月草
なかでも水洗いでよく色の落ちる代表的なものは、露草(月草)の花の汁です。この青花は、友禅染やその他の模様染の下絵を描く時の材料として利用されてきました。すぐに落ちることが分かったうえで、使っていました。

つきくさの うつろひやすく おもへかも あがもふひとの こともつげこぬ
万葉集、巻第四、相聞、五八三、
思いを寄せる人(は) 露草染のよう(に) 伝言さえも 託してこない

・草や花や色と染
一般に花の色素は、その色が日光や大気に弱いので、しばらく置くと、自然に褪色あるいは変色してしまって、大抵は茶色になってしまいます。そして大体において、草や花、葉や皮とか、あるいは実の色というものは、全く染料にはなりません。
ところがその中でも、天然の色合いの中に染料を含んでいて、その色がそのまま染色に利用し得るものが幾つかあります。しかしそれは、ほんのわずかなものに過ぎません。

参照:「日本の草木染」上村六郎 (著)