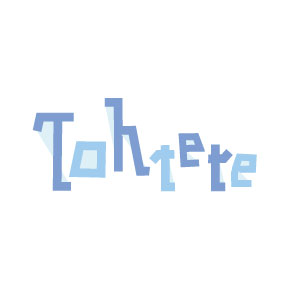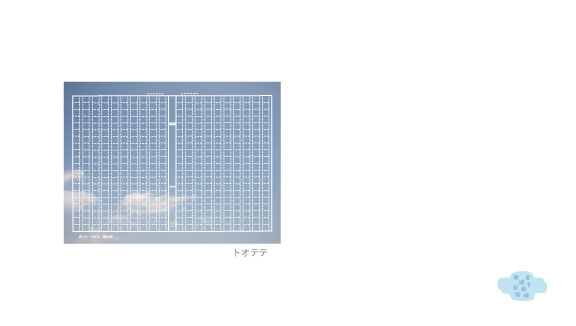序:暮らしと染色
5.たれゆへに

・花摺りと草摺り
奈良時代 (710~794)に 、実際には、既に立派な染色が知られていたものの、儀礼として、または、趣味的な意味で、花摺りを、実際の染色に利用することがありました。朝廷関係の人達の花摺りなどは、このためです。
そしてこの時代には、進歩した染色の恩恵にあずかることのなかった人達や、地方の人達などにおいて、少なくとも、実用的な意味での、草摺りがありました。例えば、しのぶの葉、めはじきの葉、椿 (つばき) の葉などは、それです。これらの葉は、変・褪色するのが遅く、いつまでも緑色を失わずにいます。

・搾り染と移し染
花摺りと草摺りのやり方には二つあります。一つは、搾り染です。これは、その搾り汁でいろいろな模様などを搾りつけて染める方法です。もう一つは、移し染です。これは、花や葉をそのまま裂(きれ)や紙などの上に置き、それを上からたたいて汁を出し、その形のままの模様を移し出す方法です。
”乱れる”というのは、移し染の場合に、形をそのまま出すのが容易ではないという意味です。 ”もち摺り” というのは、”用い摺り”、用いて摺ったということです。
江戸時代 (1603~1868) の安物の蚊帳 (かや) は、椿 (つばき) の葉で染めていました。そして、めはじきの葉は万葉集に、土針 (つちはり) という名で、摺り染の材料として出ています。また、しのぶの葉は、形も好ましく、色も丈夫で、古くからよく用いられていました。

みちのくの しのふもちすり たれゆへに みたれそめにし われならなくに
古今集、巻十四、恋歌四、七二四
こんな乱れ模様 (は) 誰のせいまるで 陸奥信夫群 (の) 摺り衣のよう (に)

参照:「日本の草木染」上村六郎 (著)