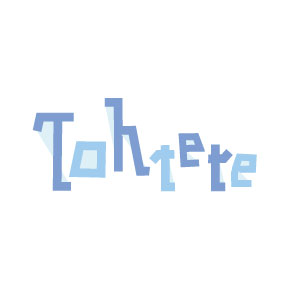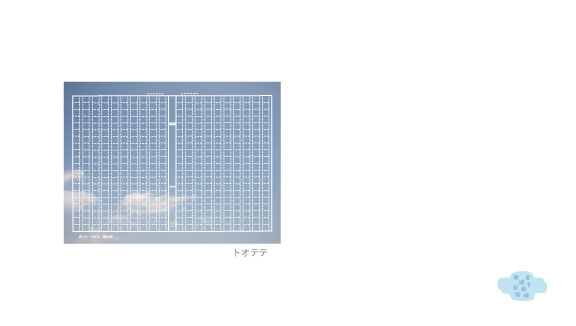序:暮らしと染色
6.複雑な成分

・静かな色
古い時代の染色品の持つ、色の落ち着きや調和の美しさは、いったいどこから来ているのでしょうか。染色において、色が落ち着いているというのは、色が暗いとか、くすんでいるということではなく、明るい色でありながら、それでいて少しも、けばけばせずに、やわらかい、ふっくりした、裂(きれ)の底から匂うて来るような、そんな静かな美しさのことです。

・風土と色の感じ方
どういう色が美しく感じられるのかということは、その土地の風土とかなり関係します。一般に、欧米のように、湿度の低い、空気の乾燥した、光線の明るい土地では、色は出来るだけ明るい方が美しく見えます。しかし、日本のように、湿度の高い、光の比較的に暗い土地では、明るすぎる色は、かえって、けばけばして、落ちつきがなく、美しい感じを与えてくれません。

・瞳と色の感じ方
黒茶の瞳の人は、瞳孔からの光のみで、色を純粋に、正確に確認することができるために、明るい色は、どぎつく感じ、渋い色、つまり色相の複雑な、落ちついた色は、美しく感じる性質があります。そして、その一方で、青い瞳の人は、瞳孔の外側の、青眼の部分から、少し青味をもった光が漏れて来て、明るい色を見ても、けばけばしくなく、かえって、かなり明るい、はっきりした色でないと、色の感じ方が、いくらかぼんやり感じる性質があります。

・色合いの成分
天然染料の染色の美しさは、どのようにしてやって来るのでしょう。また、その調和の良さは、なにが原因なのでしょう。その最も主な答えは、天然染料の成分の複雑さにあります。天然染料は、一般に、その主成分のほかに、他のいろんな色素や、その他の諸成分が混合されていて、そして、それが働いて、染色したものの、出来上がりの色を、いろいろと複雑なものにしているのです。

参照:「日本の草木染」上村六郎