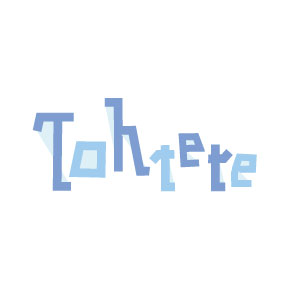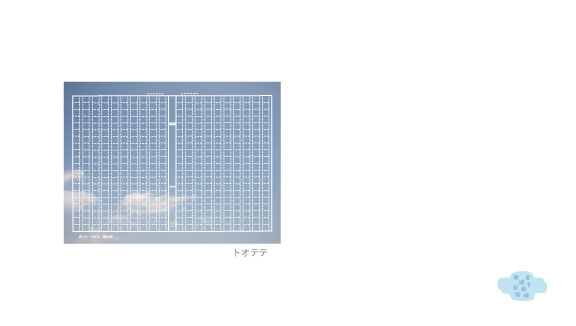序:暮らしと染色
8.自然染色の歩み ( 二 )

・浸染と媒染
初期浸染の時代を経て、やがて、灰汁 (あく) 媒染や鉄媒染というような、媒染剤による染色が、行われるようになったのは、どのようにしてなのでしょうか。

灰汁媒染は、古くから、布の漂白や着物の洗濯、あるいは、体の垢を落とすのに、広く灰汁が使われていたことから、なんらかの折に、この灰汁と薬料の液とが一緒になったことで、はじめて美しい色が出来てくるのを知ったのだと言われています。

鉄媒染による黒染などは、タンニン剤である櫟(くぬぎ) の実とか、榛の木 (はんのき)の実 (やしゃぶし) のようなものを、薬として煎じて飲む時に、その容器に鉄製のものを使ったのが原因で、また後には、飲料にならないような、鉄分を多く含んだ天然水を使っても、同様に、黒染などが出来ることが分かりました。

具体的に、どこの田の泥水が黒染に適するとか、あるいは、そこの井戸の水が、とかいうことは、その土地で、実際にいろいろとやってみて、経験として知っていったものでしょう。例えば、奄美大島で大島紬の黒味をつけるために使っていた、山の上の田んぼの泥水とか、あるいは、各地に知られている「弘法さまの井戸」というのは、その良い例です。

参照:「日本染織辞典」上村六郎